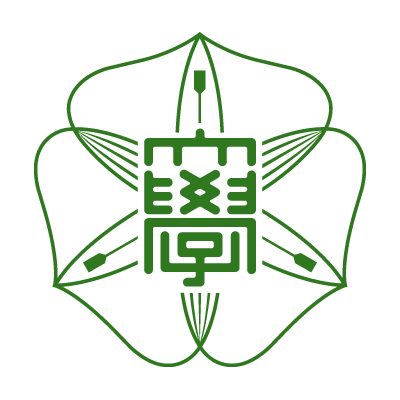[ English ]
原子核は,数個から数百個からなる核子(陽子と中性子)から構成される有限の量子多体系であり,核力と呼ばれる力によってまとめられている。クーロン力などと比べ核力の形は非常に複雑で,それ自体が研究対象でもある。このような複雑な核力が支配する原子核は,有限量子多体系に特有の豊富で興味深い現象を示し、その研究対象は多岐にわたる。それと同時に,未解決の問題も数多く存在する。現在までに数千種類の原子核の存在が理論計算によって予言されているが,特に近年,天然には安定に存在しない短寿命な原子核(不安定核と呼ばれる)が低エネルギー加速器実験によって人工的に生成されるようになり,原子核物理学の研究対象は大きく拡大した。原子核では,重力を除く自然界の基本的な相互作用が重要な役割を果たすため,低エネルギーでの原子核の構造と動力学の理解は,物質の起源や初期宇宙での重元素合成過程,現在知られている基本的対称性の検証など基礎物理の問題を解く鍵ともなる。北海道大学原子核理論研究室では,量子多体系としての原子核の構造と反応に関する主に以下の問題を理論的に探求している。
集団運動の微視的記述
原子核では,表面の変形による振動や,核全体が楕円体変形して回転運動が起きる。これらは多数の核子が関与するため集団運動と呼ばれ,核子間に働く核力の複雑さからは想像のつかないほどの単純で美しい対称性と規則性が,特徴的な振動・回転励起スペクトルや電磁遷移のパターンとして観測される。有限量子多体系がどのような幾何学的形状を持つのか?それを決定する微視的なメカニズムは何か?これらの疑問は,A. Bohr, B.R. Mottelsonら(1975年ノーベル物理学賞)による集団運動の統一模型が提唱されて以来,原子核物理学の中心的な問題の一つであり,一般の量子多体系の物理にも通じる。当研究室では,核子多体系の密度汎関数理論(Density Functional Theory)と,集団運動の代数模型である相互作用するボソン模型(Interacting Boson Model)を融合させた手法をオリジナルに提唱・発展させており,特に重い(多数の核子からなる)原子核の構造,変形,集団励起を微視的かつ統一的に記述するための理論的枠組みの構築に取り組んでいる。近年では、形状の共存や洋梨型変形をはじめとした新奇な核変形について,その微視的な記述に関する研究を行っている。さらに,世界中の大型加速器実験が研究対象とする重い不安定核のこれらの現象に関して,国際的な理論・実験共同研究を展開している。
形状の相転移と共存
原子核の形状は,核子数の増減に伴って振動状態から変形回転状態へと遷移する,相転移が起きる。形状の相転移は核構造の包括的な理解につながることから実験・理論的に大きな注目を集めている。我々は,微視的DFTに基づいてこのような現象を記述する研究を進めている。最近では,質量数が奇数の核種に関する,相互作用するボソン・フェルミオン模型ハミルトニアンをDFTから導く方法論を提唱し,偶奇核Eu同位体の球形から変形状態に至る形状遷移を再現することで,その有効性を示した。また,機械学習を用いたIBMパラメータの決定法の開発も進めている。さらに,重い不安定核においては基底状態近傍に複数の変形状態が現れる「変形の共存」と呼ばれる現象が知られており,実験・理論ともに大きな注目を集めている。変形の共存はポテンシャルエネルギー上の複数の最小点となって現れるが,これを集団運動模型やIBMのハミルトニアンに写像することにより,変形共存とそれを特徴づける低エネルギー0+励起状態やその電気的単極子(E0)遷移などの分光学的性質を解析する研究を進めている。
高次変形
核変形は,最低次の4重極モードが最も支配的である。ある特定の核子数34, 56, 88, 134などをもつ原子核においては,主殻内でパリティの異なるnormal parity状態とunique-parity状態との結合によって8重極相関が強まり,洋梨型変形の8重極変形が生じると考えられる。安定な8重極変形は荷電・パリティ不変性の破れをもたらし,素粒子の標準模型を超えた新しい物理を示唆する電気双極子モーメント(electric dipole moment)の観測実験に必要な知見を与える。8重極変形は近年のCERN HIE-ISOLDEなどでの不安定核ビームを用いた実験研究で盛んに研究されている主要なテーマの一つである。我々は4重極変形を表すボソン自由度に加え,8重極変形に対応するfボソン自由度を持ったIBM (sdf-IBM)を導入し,その相互作用強度をDFT計算から決定する方法を開発・発展させてきた。この手法を用いることで,正・負パリティ状態とそれらの間の4重極(E2)遷移,8重極(E3)遷移などの電磁遷移を微視的理論に基づいて計算することが可能としてきた。
原子核の集団励起において,基底状態付近での回転バンドなどの状態は正のパリティを持ち,ほとんどの場合は4重極変形自由度によって説明される。その一方,基底バンドの高スピン状態では4重極自由度だけでは記述できない場合があり,さらに高次な核変形自由度として16重極(hexadecapole)モードを導入する必要が示唆される。本研究では,4重極 – 16重極変形を拘束条件とした相対論的DFTに基づいた平均場模型計算を行い,希土類領域の変形核の多くが有限の16重極変形を持つことを示した。これを対応する sdg-IBMハミルトニアンの期待値に写像することで,4重極 – 16重極集団運動を記述するためのIBMのパラメータを決定した。このようなHexadecapol変形を導入することで,振動・変形核の高スピン状態を精度良く記述することが示され,さらに振動核の低スピン状態のエネルギー準位の記述を大幅に改善することに成功してきた。これらの知見は,hexadecapole変形自由度が集団運動の記述において重要であることを示唆している。
原子核の基本的崩壊過程
原子核のβ崩壊は,中性子(または陽子)が陽子(中性子)に変換される基本的な放射性崩壊である。低エネルギー領域での原子核構造を調べるための実験的手法であるだけでなく,初期宇宙における重い原子核の生成をはじめとする天体核現象を理解するのにも重要な役割を担う。我々は,個々の原子核(偶偶核,偶奇核,奇奇核)の低エネルギー励起構造と,β崩壊をconsistentに記述するための枠組みを,DFTとIBMの枠組みを用いて開発しており,これまで中性子過剰な重い不安定核におけるβ崩壊の崩壊率の計算に適用し,模型の精度向上などの課題に取り組んでいる。
隣り合う偶偶核の間で二つの陽子(中性子)が二つの中性子(陽子)に同時に変換される二重β崩壊と呼ばれる稀崩壊も知られている。この過程においては通常,二つの電子(または陽電子)と反ニュートリノ(ニュートリノ)が放出される。この二重β崩壊ではニュートリノが放出されるので2ニュートリノ二重β崩壊と呼ばれ,標準模型において許容される核崩壊である。その一方,ニュートリノが放出されない二重β崩壊(ニュートリノレス二重β崩壊)が理論的には予想されている。これは電弱相互作用の対称性や不変性が破れることを意味し,またニュートリノの性質(DiracまたはMajorana粒子),質量や階層に関する知見を与えうるため,世界中の地下実験施設でその検出に向けた実験が実施,計画されている。原子核分野の貢献は,二重β崩壊の核行列要素(Nuclear Matrix Element)の理論計算であるが,崩壊過程に関わる個々の核種の低エネルギー構造に精確な記述を与える理論的枠組みが求められる。NMEの現在までに行われた理論計算では,模型によって理論値に大きな違いがあり,その違いをもたらす理論的不定性の解析が理論分野の大きな目標と言える。我々は,DFTからの写像によってIBMを定式化する手法を用いて,ニュートリノレス二重β崩壊NMEを計算する枠組みを開発している。